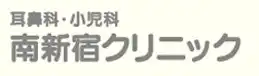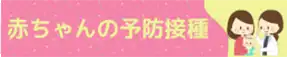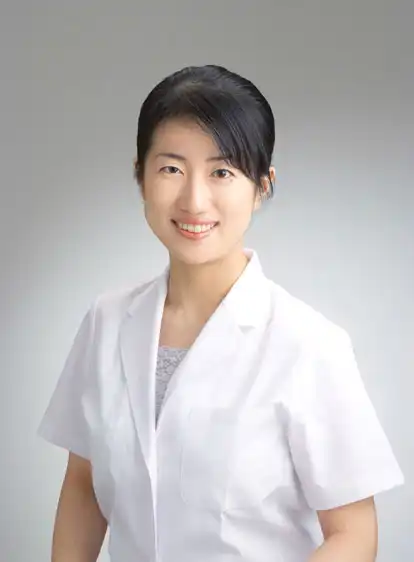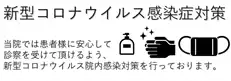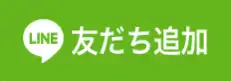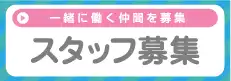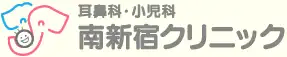小児用肺炎球菌ワクチン(PCV15)(不活化)
- 肺炎球菌感染症とは
- 鼻やのどにいる肺炎球菌が血液の中に入り、細菌性髄膜炎や細菌性肺炎などを起こし、死亡や重い後遺症が残ることもあります。肺炎、菌血症、重い中耳炎の原因にもなります。
肺炎球菌感染症は、乳幼児と高齢者で頻度が高く、2/3が抗菌薬への耐性化が進んでいます。細菌性髄膜炎の場合、Hibより予後が悪い(死亡・後遺症例)ことが知られています。小児でワクチンの接種率が高まれば、高齢者への間接効果が望めます。 - 接種時期と回数
- 生後2ヵ月~6ヵ月に接種開始の場合、全4回
(27日以上の間隔をあけて3回、生後12ヶ月から15ヶ月になるまでの間に、3回目から60日以上の間隔をあけて1回)
2024年4月から従来の13価ワクチン(PCV13 :13種類の肺炎球菌に予防効果があるワクチン)が
15価ワクチン(PCV15 :15種類の肺炎球菌に予防効果があるワクチン)に切り替わりました。
15価ワクチンは、13価ワクチンに新たに2種類の抗原(血清型22F、33F)を加えたワクチンです。
現在、接種が可能な13価ワクチンと比較して、同等以上の有効性が期待できるほか、副反応・安全性に差がないため安心して接種いただけます。また、13価の肺炎球菌ワクチンの4回接種が完了していない方は、2回目、3回目など途中からの15価ワクチンへの切り替えも可能です。15価ワクチンの切り替え接種をご希望の方は受付へお声がけください。