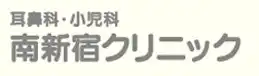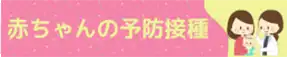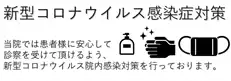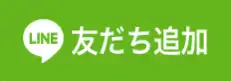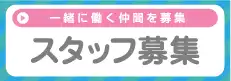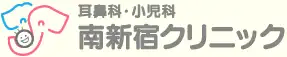赤ちゃん夜泣き
赤ちゃんの夜泣き
- 夜泣きとは
夜泣きは、赤ちゃんや小さな子どもが夜中に目を覚まして泣いてしまうことを言います。
特に病気というわけではなく、お子さんの成長過程でよく見られる自然な現象の一つでもあります。
しかし、夜泣きが続くと赤ちゃんやお子さんが寝不足になったり、不規則な生活リズムになったりするだけでなく、保護者の方の睡眠不足や免疫力の低下、体調を崩しやすくなるなどの影響が起きてしまうこともあります。
赤ちゃんや子どもの体調だけでなく、家族の体調や生活にも影響するほか、知らず知らずのうちにストレスが溜まってきてしまうこともあるため適切に対策していくことが大切です。
- いつから始まるの?
生後6ヶ月を過ぎると、お母さんからもらっていた免疫が少なくなり、自分で免疫を作り始めます。この時期前後から、一般的には風邪をひきやすくなります。お子様の発熱の原因の多くは、ウィルスなどの風邪によるものです。
しかし、ウィルスなどが直接お熱を出しているわけではありません。体に入ってきたウィルスなどを増えにくくするため、体の免疫反応が働いた結果、お熱が出ます。体の免疫は一度戦った相手を記憶して、同じ外敵が入ってきたとき倒しやすくする能力も持っています。つまり、風邪で発熱するたびに新たな免疫を獲得して成長していくとも言えるでしょう。
風邪の原因となるウィルスはとても多く、200種類以上と言われています。治ってもすぐに違うお風邪をひいてしまうことがあるのはこのためです。大人は成長過程で既に免疫を持っていることが多いため、こどもに比べて熱を出しにくい傾向があります。
- 赤ちゃんはなぜ夜泣きするの?
夜泣きの原因は分かっていません。ですが、生まれたばかりの赤ちゃんは、昼と夜の区別がまだ十分についておらず、少しずつ体内時計が整っていく途中で夜泣きが起こることが多いことも理由の一つと考えられています。
また、日中に泣く時と似た理由で夜泣きが起こることもあります。夜泣きの理由
・お腹がすいた
・おむつが濡れているなどの不快感
・睡眠リズムが整っていない
・ママやパパと離れる不安
・暑い・寒い・騒がしい・明るいなどの環境
・熱がある
・体のどこかが痛い(湿疹や傷、打撲など)
・体調が優れない
・不安な気持ちや恐怖、ストレスなど
1歳を過ぎると、夜泣きの理由も少し変わり、体の成長や心の発達と関係していることが多くなります。
まだ言葉で上手に伝えられないので、不安な気持ちや体の不快感を「泣く」という形で表現することがあります。
- 赤ちゃんの眠りの特徴
赤ちゃんの睡眠サイクルは大人とはちょっと違います。
大人の睡眠サイクルが約90分なのに対し、赤ちゃんは睡眠が未発達で短いのが特徴。目が覚めやすく、自分でまた眠りにつくのが難しいため夜泣きをしやすいです。
また、赤ちゃんは浅い眠りの時間が大人より長いので、ちょっとした物音や不快感で起きやすいです。
- 成長する子どもの眠り
成長とともに睡眠サイクルは徐々に大人に近づきますが、睡眠をコントロールする力は発達途上なため、目が覚めて暗い中で不安になったり、体の不快感で起きてしまったりして夜泣きをすることがあります。
また、夢を見る能力も発達してくると、怖い夢を見て泣き出すことも出てきます。
- 夜泣きへの対応
夜泣きは赤ちゃんの成長過程の一部なので、特別な治療をしないことがほとんどですが、「夜中もしっかり寝てほしい」というのが正直なところ、という保護者の方も多いかと思います。
私自身も子育てをする中で夜泣きを経験してきたのですが、毎日となると体も心も疲れてきてしまったのを覚えています。
「今日は夜泣きがなかったな」と1日でもしっかり寝てくれると、それだけでも安心できたり、しっかり寝れたねと嬉しくなったり、体もリフレッシュした気分になりますよね。
子育てを頑張るご家族の方にとっても、そうした日が少しずつ増やしていけるように、子どもの発達発育と夜泣きの原因から対応のポイントをお伝えしていきます。夜泣き対応のポイント
〇寝る前に適量のミルクや母乳、離乳食をあげる
赤ちゃんの胃は小さく、大人に比べてお腹がすきやすいので寝る前に母乳やミルクをあげるとお腹が空いて目が覚めることが減ってきます。ミルクを飲んだあとはげっぷも忘れずにしましょう。
〇寝る前におむつチェック
寝る前におむつが濡れて無いかチェックしてあげましょう。おむつの中の不快感も目が覚める要因になります。
〇毎日同じ流れで寝るようにする
お風呂に入った後に着替える、絵本の読み聞かせをする、就寝など特定の流れを作ることでもうすぐ寝る時間と理解しやすくなります。寝るまでのリズムを整えてあげることで、赤ちゃんも落ちついて就寝できるようになります。
〇環境を整える
赤ちゃんは体温が高く、汗をかきやすいので、温度や湿度を快適に過ごせるように整えましょう。部屋が十分に暖かい場合には、掛布団もいりません。
- 夜泣きの治療・相談
夜泣きの治療というと、〇〇が即効性がある!という特別なものは残念ながらありません。
しかし、熱がある、体が痛い、肌がこすれてかゆいなど体の不調や不快感がある場合には、その原因をしっかり治療していくことが大切です。
子どもは体温も高く、熱が出ていても気づきにくい、痛みを具体的に伝えることが難しいこともあり、「お腹が空いているから」「よくわからない」けど夜泣きが続く場合には、他の原因が無いか観察することも大切です。
日々の夜泣きに悩んでいる、夜泣きの対策を個別に相談したいといった場合には南新宿クリニック耳鼻科・小児科へお気軽にご相談ください。 ご来院前に、こちらの「小児科」をご予約ください。
<監修者情報>
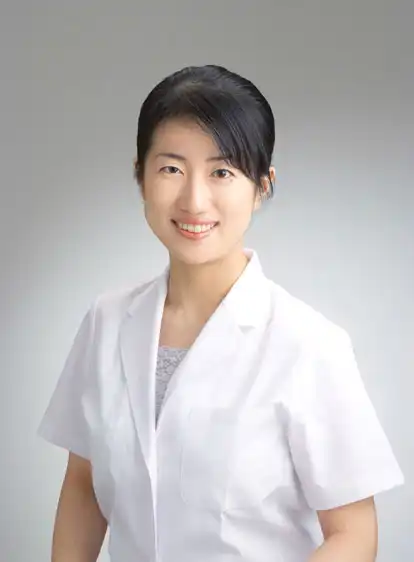
木村 絢子 副院⻑
平成19 年東京慈恵会医科大学卒業。研修医としてプライマリーケアを学び、小児科全般の治療に従事。その後、同大学医学部附属第三病院にて病棟⻑として勤務。小児科疾患以外にも、日本アレルギー学会アレルギー専門医として、小児アレルギー疾患を得意とし、お子さま の健やかな成⻑を医療を通じて⾒守る医師として活躍。
日本小児科学会認定小児科専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医